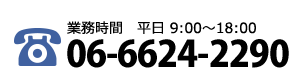| 遺言書 |
司法書士の下室です。
久しぶりの投稿になります。
さて、近時、遺言書の作成の依頼が非常に多くなったように思います。
「終活」などの言葉もメディアやネットなどでよく聞くようになりました。そんな影響があるのかもしれませんね。
遺言書には、主に2つの方式があります。
①公正証書遺言
こちらは、公証人役場で、公証人によって作成される遺言書です。
実務上は、弁護士や司法書士などが、遺言をする方からヒアリングを重ね、税務上の問題なども検討したうえで、その方の遺志を文章にします。
この遺言書の案を公証人に予め見てもらい、作成の当日に、公証人が遺言者の意思を確認して作成します。
そのときに、証人2名の立会も必要になりますので、弁護士や司法書士などが立ち会うことが多いです。
公正証書遺言は、遺産の種類が多岐にわたり、各遺産ごとに個別に遺言を残したいときなどに向いています。
また、後日、遺言書の内容にあらそいが生じた場合など、公証人が関与していることもあり無効になりにくと言われています。
②自筆証書遺言
こちらは、文字通りすべて自筆で遺言者自身が遺言書を書く方式です。
基本的に、「全文」自筆で、「日付」「氏名」「押印」が必要になります。
自筆証書遺言は、比較的シンプルな内容の遺言書を作成する場合に向いています。
全文自筆なので、あまり複雑で長文となると、全部自筆するのに労力を要してしまします。
また、亡くなられた後に、家庭裁判所に対して「検認」手続きをする必要があるため、これまではあまり利用されなかったように思います。
しかし、最近になって法務局による「自筆証書遺言保管制度」が新たに設けられました。この制度を利用すると「検認」が不要になるのです。
そのため、自筆証書遺言を作成して、法務局に保管する方が非常に多くなりました。
こちらの制度を利用するには、遺言者本人が法務局に出向く必要があるので、少し面倒ですがコスト的に非常に安価なので、今後益々利用者が増えると思います。
いずれにしても、遺言をする方の遺志を「文章にする」というのが少し難しいので、作成する場合には専門家にご相談されることをお勧め致します。
|
 2025/06/25
2025/06/25
|